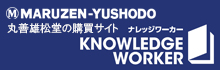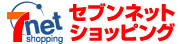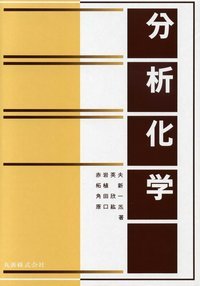
内容紹介
化学反応の選択性を利用したすぐれた分離法の確立の観点から、分析化学で用いられる基礎原理について平易に解説。また分析対象の超微量化への対応、古典的な分析法と機器分析法の橋渡しを行い、原理、特徴、用途を具体的に記述。
目次
1 序論
2 分析化学の基礎
2・1 水
2・2 強電解質と弱電解質
2・3 酸―塩基の概念
2・4 ルイス酸―塩基の硬さ,軟らかさと定性分析
2・5 電解質溶液中での反応速度
2・6 電解質溶液中での化学平衡
2・7 化学平衡に及ぼす電解質濃度の影響
3 分析に用いられる化学平衡
3・1 酸―塩基平衡
3・2 沈殿平衡
3・3 酸化還元平衡
3・4 錯形成平衡
4 古典的定量分析法
4・1 容量分析
4・2 重量分析
5 分離と濃縮
5・1 序論
5・2 蒸留・蒸発による分離
5・3 沈殿による分離と濃縮
5・4 抽出による分離と濃縮
5・5 イオン交換法
5・6 膜分離
5・7 クロマトグラフィー
5・8 電気化学的分離
5・9 固体試料中の可溶微量成分の分離
5・10 プリコンセントレーション(予備濃縮)
6 試料採取および調整
6・1 試料採取
6・2 試料の粉砕
6・3 分析試料中の水分の取扱い
6・4 試料溶液の調製
7 分析値の取扱い
7・1 誤差の種類
7・2 正確さと精度
7・3 測定値の表示
7・4 正確さと制度の表示
7・5 誤差の伝播
7.6 かけ離れた測定値の棄却
7・7 最小二乗法
8 機器分析
8・1 機器分析概論
8・2 電磁波および電子線を利用した分析法
8・3 原子スペクトル分析法
8・4 磁気共鳴を利用した分子スペクトル法
8・5 光を利用した分子スペクトル分析法
8・6 X線分析法と電子分光法
8・7 電気化学分析法
8・8 流体を利用する分析法
8・9 その他の分析法
9 分析化学の新しい発展
9・1 分析化学の発展小史
9・2 分析化学の諸課題
9・3 複合化・知能化・自動化が進む分析化学
出版社からのメッセージ
本書籍は価格変更に伴い、ISBNを変更しました。内容に変わりはありません。